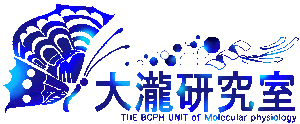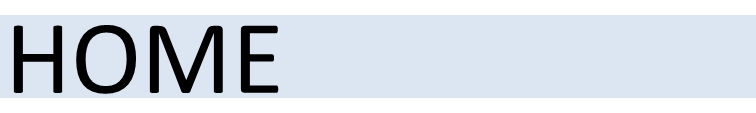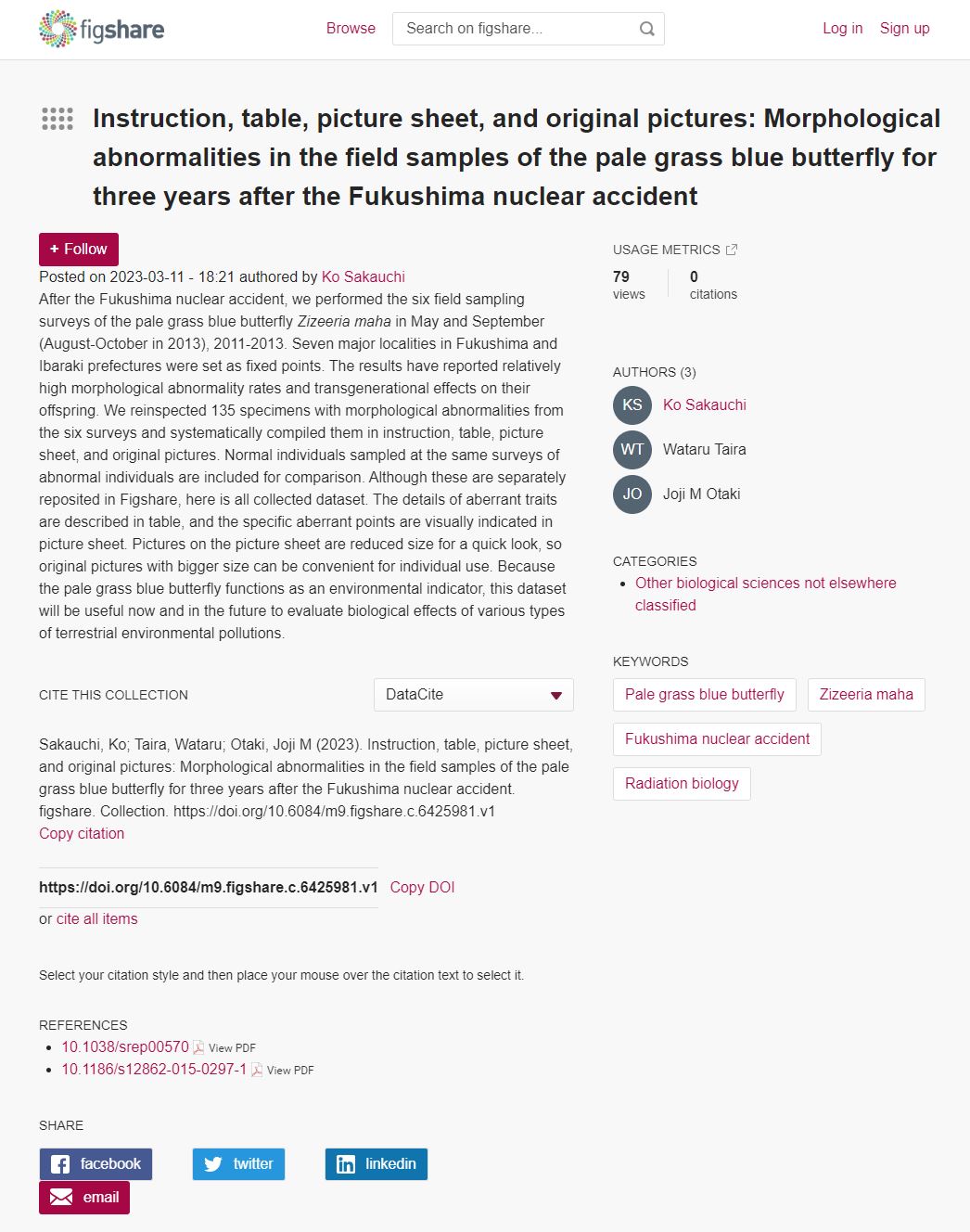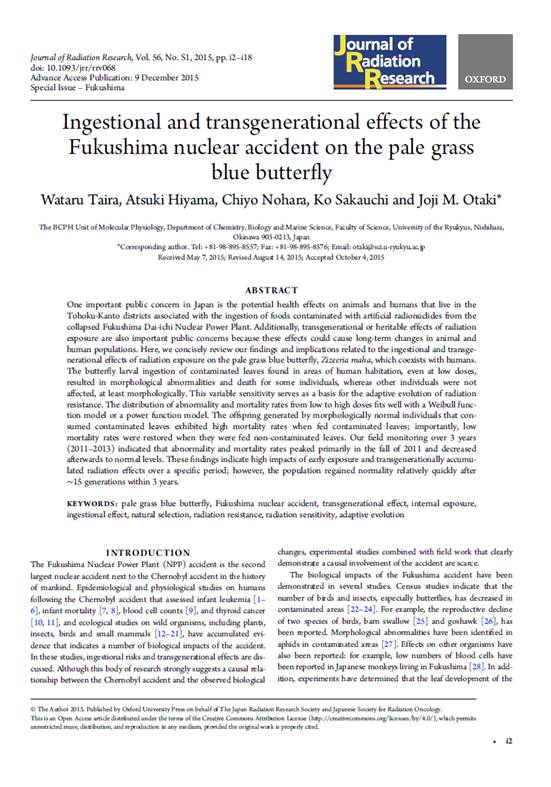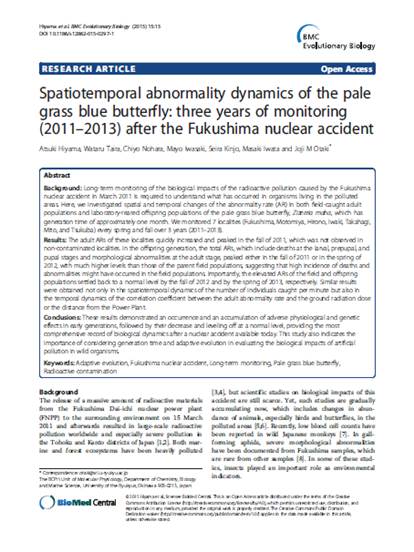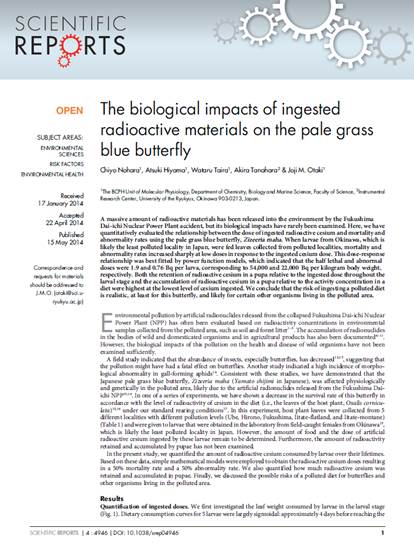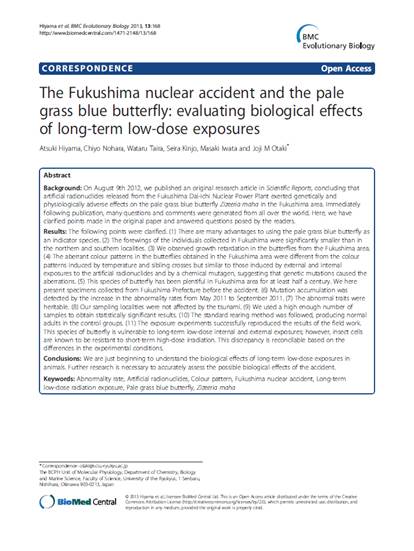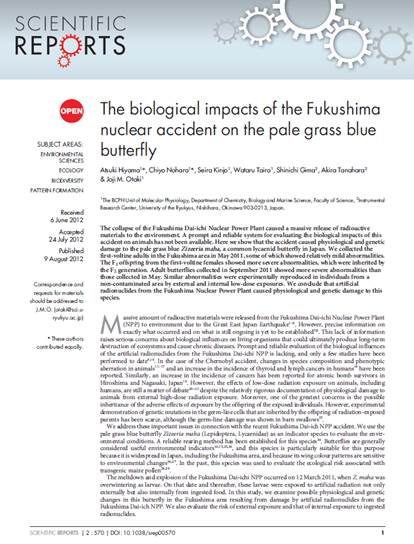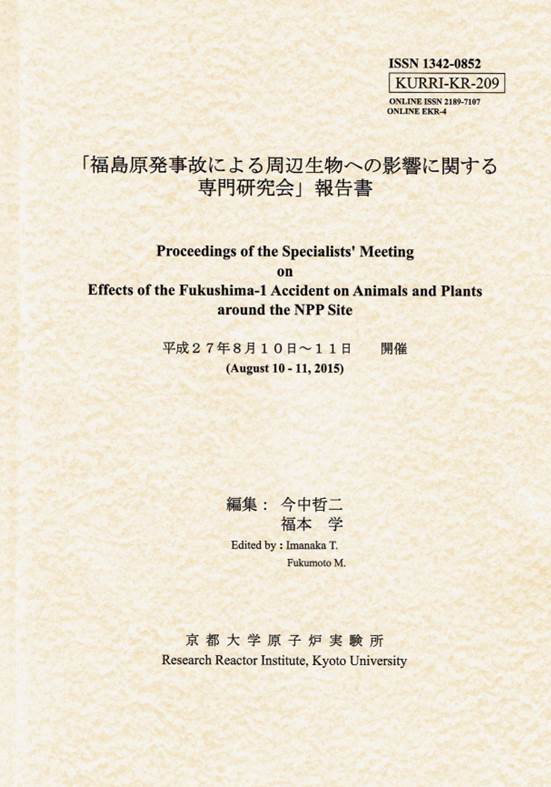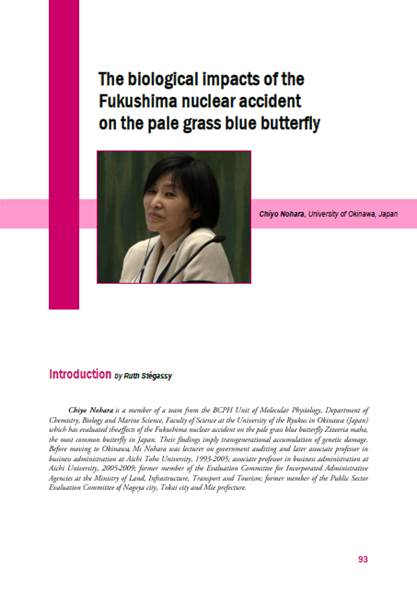フクシマプロジェクト
大瀧研究室では、2011年の事故直後から福島県周辺で放射能汚染の生物学的影響について調査を行ってきました。このページでは、それらの研究の成果や参考文献などを紹介します。
大瀧研から発表したフクシマ論文 その他の出版物 大瀧研から発表した関連論文
ABTプロジェクト 取り上げていただいたメディア 参考文献集
大瀧研から発表した論文
※論文中の図や表は日本語訳版には付けておりません。日本語版だけでなく、原文(英語版)も併せてダウンロードして読んでいただきますよう、よろしくお願いたします。
![]() 2023/05/18
2023/05/18
Imaging Plate Autoradiography for Ingested Anthropogenic Cesium-137 in Butterfly Bodies: Implications for the Biological Impacts of the Fukushima Nuclear Accident
チョウの体内に取り込まれた137Csのイメージングプレート・オートラジオグラフィー:福島原発事故による生物学的影響への示唆
[最新論文(第23報)] 2011年3月の福島原発事故は、ヤマトシジミに生物学的影響をもたらしたが、少なくとも一部の影響は、宿主植物であるカタバミを介した「フィールド効果」によるものだろう。しかしながら、影響の全体像を把握するためには、直接的な被曝影響も評価する必要がある。本稿では、イメージングプレート・オートラジオグラフィーを用いて、実験下で摂食した137Csの成虫における体内分布を調べた。幼虫期に摂食された137Csは、大部分が羽化時に蛹の抜け殻や老廃物として排出されるものの、成虫の体内にも取り込まれ、メスでその傾向が顕著なことが分かった。成虫における137Csの蓄積は、腹部で最も多く、次いで胸部、その他の器官となった。このことは、生殖器官での137Csの蓄積が、活性酸素種による継代的あるいは母系的な悪影響を生殖細胞にもたらす可能性があることを示している。また、137Csの蓄積は、2011年9月と2016年9月に採集された野外個体でも見られた一方で、2011年5月では見られなかったが、これは、先行研究による形態異常率の動態と一致する。以上より、これらの結果は、福島原発事故の野外における多面的な生物学的影響の総合的な理解に役立つだろう。
![]() 2023/03/11
2023/03/11
Instruction, table, picture sheet, and original pictures: Morphological abnormalities in the field samples of the pale grass blue butterfly for three years after the Fukushima nuclear accident
説明書、表、写真一覧、個別写真:福島原発事故後3年間における野外採集ヤマトシジミの形態異常
[画像データの公開] 福島原発事故後、2011-2013年の5月および9月(2013年は8-10月)の全6回にわたり、ヤマトシジミの野外採集調査を行った。福島県と茨城県の主要7地点を定点とした。結果として、高い形態異常率と子孫への継代的な影響が報告されている。我々は全6回の調査から得られた135の形態異常個体を再検証し、説明書、表、写真一覧、個別写真として体型的にまとめた。比較のため、異常個体と同様の調査で得られた正常個体も含めている。これらは別個Figshareにおいて公開されているが、ここでは全てのデータをひとつに集約した。異常形質の詳細は表にまとめ、特定の異常箇所は写真一覧で視覚的に示している。写真一覧上の写真は概観用のためサイズが小さいが、個別の利用に備えてサイズの大きな元の写真も調査回ごとに用意した。ヤマトシジミは環境指標生物として機能するため、このデータセットは、あらゆる環境汚染による生物学的影響を評価するために、現在そして未来においても有用であろう。
2022/04/26
The second decade of the blue butterfly in Fukushima: Untangling the ecological field effects after the Fukushima nuclear accident
福島のシジミチョウの次の10年:原発事故後の生態学的フィールド効果を紐解く
[最新論文(第22報)] 福島原発事故後、最初の10年間に、事故の生物学的影響に関する多くの野外調査が報告されてきた。昆虫は一般的に放射線被曝に耐性があるとする線量測定に基づく見解に反して、“野外”においては低線量放射線被曝でさえヤマトシジミに不利な影響をもたらすことが、一連の野外調査および実験による研究で証明されている。一方で、“実験”条件下では、ヤマトシジミは人工放射性セシウム(Cs-137)の高濃度経口投与に対して耐性を持つことが示されている。この野外と実験室間のパラドックスは、生態学的なフィールド効果によって説明可能である。例えば、野外での放射線ストレスが宿主植物に生理的、生化学的な変化を引き起こし、それが栄養学的にチョウの幼虫に影響するのである。チョウを基盤とした福島研究の次の10年は、このような野外での悪影響がどのように生じるのかを明らかにすることに費やされるだろう。宿主植物の栄養成分の変化は、チョウの生理機能に影響するかも知れない。また、宿主植物が植食性昆虫に影響を与える二次代謝物を増加させる可能性もある。さらに宿主植物は、放射能汚染地域の内生土壌微生物の変化によって影響を受けることも考えられる。もしこれらの結果が実証されれば、チョウとその宿主植物、そして土壌微生物間の繊細な生態学的バランスが、福島の放射能汚染によって影響を受けてきたことが明らかになるだろう。そしてそのことは、環境政策と人間の健康に重要な意味をもつ。
2022/04/20
Ingestional Toxicity of Radiation-Dependent Metabolites of the Host Plant for the Pale Grass Blue Butterfly: A Mechanism of Field Effects of Radioactive Pollution in Fukushima.
福島の放射能汚染地域に生育するカタバミのメタボロームプロファイル: 主要代謝物における線量依存的変化
[第21報] 福島原発事故の生物学的影響は、ヤマトシジミとその宿主植物であるカタバミを含む様々な生物種で報告されてきた。カタバミは、低線量被曝に応じて種々の二次代謝物を増加させ、このことが福島でのチョウの高い死亡率や異常率をもたらす可能性がある。しかしながら、このフィールド効果仮説は実験的に検証されていない。ここでは、幼虫への人工飼料を用いて、先行のメタボローム研究で注釈の付けられた3つの線量依存的な植物代謝物、ラウリン酸(飽和脂肪酸)、アルフゾシン(アドレナリン受容体阻害剤)、イカルガマイシン(内生菌由来の抗生物質)について、摂食による毒性を調べた。ラウリン酸またはアルフゾシンの摂取は、蛹化率、羽化率(生存率)、正常率の有意な低下を引き起こし、これらの化合物の毒性を示した。ラウリン酸は、卵-幼虫期間を有意に延ばし、幼虫の成長遅延を示した。対照的に、イカルガマイシンは、おそらく真菌や細菌から飼料を防御したために、蛹化率と羽化率を有意に上昇させた。これらの結果は、ラウリン酸等の少なくともいくつかの線量依存的な植物代謝物が、福島のチョウにおける放射能汚染の有害な影響に寄与していることを示しており、フィールド効果仮説への実験的な証拠を提供するものである。
2022/01/13
Metabolomic Profiles of the Creeping Wood Sorrel Oxalis corniculata in Radioactively Contaminated Fields in Fukushima: Dose-Dependent Changes in Key Metabolites.
ヤマトシジミの宿主植物における放射線量依存的代謝物の摂食毒性:福島の放射能汚染によるフィールド効果のメカニズム
[最第20報] 2011年の福島原発事故による野生生物への生物学的影響は、ヤマトシジミとその宿主植物であるカタバミを含む多くの生物種で研究されてきた。本稿では、2018年に福島県、宮城県、新潟県の放射能汚染地域および対照地域にて採取されたカタバミの葉を用いて、LC-MSによるメタボローム解析を行った。検出された7967個のピークを使ったクラスター分析では、放射線量に関わらず、9つの福島サンプルと1つの宮城サンプルが同一集団にまとめられ、2つの福島(飯舘)と2つの新潟サンプルはこの集団には属さなかった。しかし、93個のピークは、線量ごとに、バックグラウンド、低線量率、高線量率の3つのグループ間で有意に異なっていた(FDR < 0.05)。これらのうち7個の上方制御と15個の下方制御のピークに単一の注釈が付けられ、ピーク強度は地面線量率と各々正および負の相関があった。上方制御のピークは、クジノシドD(サポニン)、アンドラクシニジン(アルカロイド)、ピリドキサールリン酸(ストレス関連活性化ビタミンB6)、抗生物質を含む4つの微生物関連生理活性物質、として注釈が付けられた。加えて、単一の注釈のある2個のピークでは、低線量率において、最も有意に増加(K1R1H1; ペプチド)もしくは減少(DHAP (10:0); デカノイルジヒドロキシアセトンリン酸)した。このことから、カタバミは、主要な代謝物を増減させることで、福島の放射能汚染に応答していると考えられる。さらに、植物関連の内生微生物もまた汚染に応答しており、植物のストレス反応に貢献している可能性が示唆された。
2021/09/20
Metabolomic Response of the Creeping Wood Sorrel Oxalis corniculata to Low-Dose Radiation Exposure from Fukushima's Contaminated Soil.
福島の汚染土壌からの低線量被曝に対するカタバミのメタボローム応答
[第19報] 福島原発事故の生物学的影響は、ヤマトシジミ(鱗翅目シジミチョウ科)とその宿主植物であるカタバミ(カタバミ科カタバミ属)を用いて、集中的に研究されてきた。ここでは、沖縄産のカタバミの葉についてメタボローム解析を行い、福島の汚染土壌からの低線量放射線被曝に応答して上方制御もしくは下方制御される植物の代謝物を調べた。植物への積算照射線量は5.7 mGy(34 μGy/h、7日間)であった。GC-MS分析により、照射群では秩序的な減少傾向が認められ、カプロン酸、ノナン酸、アゼライン酸、オレイン酸、加えて、糖代謝経路に関わるフルクトース、グルコース、クエン酸等と注釈が付けられた。注目すべきことに、ラウリン酸と注釈付けされたピークでは増加が見られた。対照的に、LC-MS分析では、多くの増加代謝物が検出され、抗酸化物質もしくは防御経路に関連するストレス関連物質のいずれかの注釈が付けられた。単一の注釈を持つ代謝物のピークは3つで、そのうち1つはα 1 アドレナリン受容体阻害剤であるアルフゾシンであった。我々は、カタバミは汚染土壌からの低線量被曝に代謝的に反応し、それは、福島のチョウにおける発生過程の悪化をまねく生態的な"フィールド効果"をもたらす可能性があると結論付けた。
2021/02/09
Nutrient imbalance of the host plant for larvae of the pale grass blue butterfly may mediate the field effect of low-dose radiation exposure in Fukushima: Dose-Dependent Changes in the Sodium Content.
ヤマトシジミの幼虫における宿主植物の栄養不均衡が福島での低線量放射線被曝によるフィールド効果をもたらす可能性:ナトリウム含有の線量依存的な変化
[第18報] ヤマトシジミ(Zizeeria maha)は、野外における福島原発由来の低線量放射能汚染に敏感な一方で、室内飼育実験において人工飼料に添加された 137 Csには高い耐性を示している。この野外と実験室の矛盾(field-laboratory paradox)を解決するために、我々は、宿主植物であるカタバミ(Oxalis corniculata)が放射線ストレスに対して生化学的な変化を起こし、これによりチョウが野外での脆弱性を示すのではないかと仮定した。このフィールド効果仮説の検証のため、東北地方(主に福島県を含む汚染地域)、新潟地方、九州地方で、宿主植物の含有栄養成分を調べた。東北にて採取のカタバミでは、新潟のものと比べて、ナトリウムと脂質の含有量が有意に少なかった。このうちナトリウムのみで、葉内 137 Cs放射能濃度、および、地面線量率と有意な負の相関が見られた。さらにナトリウムは、他の栄養成分とも相関があった。これらの結果は、カタバミにおけるナトリウム含有量の不均衡は、放射線ストレスによって生じる可能性があり、単食性であるチョウにとって、このような栄養不均衡が、福島原発事故直後に野外にて観察された高い死亡や形態異常をもたらした要因の一つとなり得ることを示唆している。
2020/01/07
The pale grass blue butterfly in ex-evacuation zones 5.5 years after the Fukushima nuclear accident: Contributions of initial high-dose exposure to transgenerational
福島原発事故から5.5年後の旧避難区域におけるヤマトシジミ:継代効果への初期高線量被曝の寄与
[第17報] 福島原発事故の生物学的影響については様々な生物種による報告があるが、その評価は十分ではない。そこで我々は、事故による生物学的影響の残存を評価するため、事故から5.5年後にあたる2016年の9月に、福島県内の旧避難区域においてヤマトシジミ(鱗翅目シジミチョウ科)を採集した。形態異常率は高くはなかったが、初期(2011年3月)の131Iおよび137Cs地面放射能濃度と有意な正の相関が見られた。捕獲率は、初期の137Cs地面放射能濃度と負の相関傾向が認められた。形態異常率と捕獲率のいずれも地面線量(2016年9月)とは相関がなかった。一般化線形モデル(GLM)による分析でも、地面線量ではなく、初期の131Iおよび137Cs地面放射能濃度の寄与が示された。これらの結果は、主に放射性ヨウ素、放射性セシウム、そして他の核種による初期の高線量被曝により、旧避難区域における2016年現在のヤマトシジミが、深刻ではないものの、依然として影響を受けていることを示している。我々は、放射能汚染による継代効果は、事故後5.5年を経ても継続して存在しており、それは、他の経路による損傷の潜在的な寄与を無視は出来ないとしても、遺伝的変異を介しているのではないかと結論付ける。
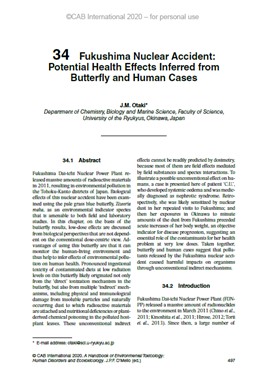
2019/12
Fukushima nuclear accident: potential health effects inferred from butterfly and human cases
福島原発事故:チョウとヒトの症例から推測される健康への潜在的な影響
[第16報] 2011年に福島第一原子力発電所は大量の放射性物質を放出し、日本の東北-関東地域に環境汚染をもたらした。この原発事故の生物学的影響は、フィールド、実験室の両方での研究に適した環境指標生物種であるヤマトシジミ Zizeeria maha を用いて調査されてきた。この章では、チョウの結果に基づき、従来の線量中心的な視点に依存しない生物学的展望から、低線量放射線の影響が議論されている。ヤマトシジミを利用する利点は、このチョウが人々の住む環境をモニターできるため、環境汚染のヒトの健康への影響を推測する手立てとなることである。このチョウでは、低線量レベルで汚染された餌に明白な経口毒性が示されるが、それは、チョウの中での「直接的な」イオン化メカニズムだけでなく、不溶性粒子や放射性物質が付着した自然に存在する塵埃による物理的および免疫学的な損傷、汚染された宿主植物の葉の栄養欠乏または植物由来の化学物質による毒性を含む複数の「間接的な」メカニズムに起源を持つ可能性がある。これらの通常は考慮されていない間接的影響は、それらのほとんどがフィールドに存在する物質との種間相互作用を介したフィールド効果であるため、線量測定によって容易に予測することはできない。この可能性のある非通常的な影響をヒトにおいても例証するために、全身性浮腫にかかりネフローゼ症候群と医学的に診断された患者「C.U.」の症例がここに示されている。遡及的に考えると、彼女は繰り返し福島を訪れる中で、放射性塵埃によって感作された可能性がある。そして、福島から持ち込まれた微量の塵埃へ沖縄で曝露されるが、その暴露の時期は病気の進行の客観的な指標である体重の急速な増加の時期に先行していた。このことは、非常に低い線量の汚染物質が彼女の健康問題に欠くことのできない役割を果たしたことを示唆している。総合して考えると、チョウとヒトの症例は、福島原発事故によって放出された汚染物質が、通常は考慮されていない間接的なメカニズムを介して、生物に有害な影響を引き起こすことを示唆している。
※書籍『A Handbook of Environmental Toxicology: Human Disorders and Ecotoxicology. 』(Edited:D’Mello JPF. CAB International, 2020.)の34節として掲載されている論文です.
2019/11/11
The pale grass blue butterfly as an indicator for the biological effect of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident
福島第一原発事故による生物学的影響の指標としてのヤマトシジミ
[第15報] ヤマトシジミ(Zizeeria maha)は2011年から福島第一原発の生物学的影響の指標として使用されてきた。様々な生物学的な側面が調べられ、形態的異常や死亡を通して福島第一原発事故の生物学的影響が指摘された。しかしながら、汚染地域におけるこのような生物学的影響の原因となるメカニズムは良く分かっていない。この論文では、福島第一原発事故後のヤマトシジミに関する先行研究や現在の研究が簡潔に概説され、フィールド効果に関する問いに答えるための新しい方針を提供する。
2019/11/04
Overwintering states of the pale grass blue butterfly Zizeeria maha (Lepidoptera: Lycaenidae) at the time of the Fukushima Nuclear Accident in March 2011
2011年3月福島原発事故時におけるヤマトシジミ(鱗翅目シジミチョウ科)越冬様態について
[第14報] 2011年3月の福島県原発事故は、福島第一原発発電所から周辺環境へ人工放射性物質の大規模な拡散を招いた。これまでヤマトシジミを用いてその生物学的影響が研究されてきたが、越冬の様態については言及されてこなかった。そこで我々は、事故当時の本種の越冬様態を明らかにするため、2018年3月および4月、2019年4月と、福島県とその周辺地域において野外調査を行った。2018年と2019年の3月には、敷き藁の下に生育する宿主植物、カタバミに隣接して、1齢から4齢までの幼虫が発見されたが、他の成長段階での個体は見られなかった。また、縦長(補足:頭部から腹部端まで)と横長(補足:胴幅)は、積算温度と有意な相関があった。そして、体サイズと積算温度における直線回帰式、および、その他のデータから、原発事故時、福島とその周辺地域でのヤマトシジミは4齢幼虫であったと推測された。本研究は、本種における事故後の被曝量を推定する今後の分析へ続くものである。
2019/09/09
Tolerance of high oral doses of nonradioactive and radioactive caesium chloride in the pale grass blue butterfly Zizeeria maha
ヤマトシジミ(鱗翅目シジミチョウ科)における、非放射性塩化セシウムおよび放射性塩化セシウムの高線量経口摂取への耐性
[第13報] 福島原発事故による生物学的影響は、ヤマトシジミ(鱗翅目シジミチョウ科)を用いて調べられてきた。以前行われた内部被曝実験では、野外にて採取された最大43.5 kBq/kg(葉)の放射性セシウムを含む汚染食草が幼虫に与えられた。幼虫は最大480 kBq/kg(幼虫)を摂取し、結果として、高い死亡率および形態異常率を示した。しかしながら、これらの結果は、セシウムの毒性学的なデータに照らし合わせる必要がある。そこで我々は、ヤマトシジミにおける非放射性塩化セシウムおよび放射性塩化セシウムの毒性を調べた。幼虫は、セシウムを含む人工飼料を食べ、最大149 MBq/kg(幼虫)の放射性セシウム(137Cs)か、もしくは、さらに多くの量の非放射性セシウムを摂取した。我々は、蛹化率、羽化率、成虫に到達するまでの生存率、翅長について検証した。野外採取の汚染食草を使用した以前の内部被曝実験とは対照的に、いかなる影響も検出されなかった。結論として、検証された範囲内においては、137Csからの電離放射線に対して耐性を持つ一方で、野外での放射能汚染に対しては脆弱であると考えられる。これらの結果は、野外における生物学的影響には、生態系システムが介在している可能性があり、放射線量のみに基づいての評価はできないことを示唆している。
2019/02/22
Developmental and hemocytological effects of ingesting Fukushima’s radiocesium on the cabbage white butterfly Pieris rapae
福島の放射性セシウムの摂取がモンシロチョウ(鱗翅目シロチョウ科)の成長および血球に与える効果
[第12報] 福島第一原発事故後、ヤマトシジミにおいては、高い形態異常率と死亡率が報告されている。しかし、これらの結果が本種に限られたものであるのかどうかは不確かであった。本研究では、福島の汚染土で栽培されたキャベツを与えた場合の成長と血球への内部被曝影響を、モンシロチョウ(Pieris rapae)を用いて検証した。汚染キャベツは、様々なレベルで低線量の人工放射性セシウム134Csと137Csを含み(自然放射性カリウム40K以下)、日本で最も汚染の少ない沖縄由来の幼虫に与えられた。すると、実験個体群において、成長や形態に関して負の影響が検出された。血リンパ中の顆粒球の割合は、カリウムではなくセシウム放射能濃度と負の相関を示し、羽化率、成虫到達率、全体正常率と正の相関を示した。以上の結果は、福島において低線量の放射性セシウム(自然放射性カリウムではない)を摂取することは、ヤマトシジミ同様モンシロチョウについても、細胞および個体レベルの両方で、生物学的に負の影響を引き起こすことを明示している。
2018/11/05
Understanding low-dose exposure and field effects to resolve the field-laboratory paradox: Multifaceted biological effects from the Fukushima nuclear accident
(野外と実験室のパラドックス)解明のための低線量被曝およびフィールド効果への理解:福島原発事故における多面的な生物学的影響
[第11報] 昨今では、福島原発事故の生物学的影響についての報告が、多様な野生生物種で蓄積されつつある。ヤマトシジミを用いての野外に基づく室内実験の結果は、この種が汚染地域由来の野外食草による”低線量”内部被曝に高い感受性を持つことを明確に示している。これらの実験結果は、高い形態異常率の見られる野外採集調査と完全に一致している。その一方で、実験条件下で化学的に純粋な放射性塩化セシウムを与えた場合の内部被曝に対しては、強い耐性を示す。この野外と実験室のパラドックスを解決するために、私は次のように提唱する。フィールド効果、つまり、既知の直接的な効果とは異なる経路を通して働く間接的な効果の集積が、野外での”低線量”被曝において重要な役割を果たす可能性を提案する。言い換えれば、線量評価によって予測される放射線量の直接的な効果のみを考慮することは、野外での被曝影響を過度に単純化し過ぎてしまうことになる。この章では、様々な野外効果について実用的な定義を示し、議論する。原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCER)の2017年白書での誤解の例についても言及する。最後に、ヤマトシジミモデルのヒトへの理論的な応用も検討する。
2017/02/11
Current status of the blue butterfly in Fukushima research
フクシマ研究におけるヤマトシジミの現状
[第10報] 福島原発事故による有害な生物学的影響は、2012年以降、ヤマトシジミ(鱗翅目シジミチョウ科)を用いて明らかにされてきたが、それらの結果は、しばしば、放射線生物学の慣例的な理解とは相反するとみなされてきた。この矛盾は、実験系や方法論の違いに端を発していると思われる。本論文では、初めに、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)による我々の研究についてのコメントに答える。UNSCEARは単位の使用および数理モデルについて「技術的な誤り」を指摘しているが、これらは誤りではなく、単位変換と数理モデル適合に付随する理論的仮説を導入しないという我々の研究哲学を反映するものである。次に、初期の2012年当時の結論を支持するため、最近の我々の研究を概観する。2011年に福島で検出された高い形態異常率と体サイズの小型化は、おそらく適応進化を経て、すでに終息していることから、現在における形態異常率や体サイズの地理的分布について全国的に調査された。相対的に高い異常率と小さな体サイズを示す地域個体群は稀で、基本的に宮城およびそれ以北地域の個体群に限られており、福島の個体群は含まれていなかった。このことは、福島では、原発事故が形態異常や小型化の原因として寄与したことを支持している。最後に、福島原発事故による生物学的影響について全体像を理解することの重要性を強調する。直接的な放射線の影響に加えて、未知の放射線に関連する二次的なメカニズム、例えば、動植物における不溶性の微粒子物質に対する免疫学的反応や栄養欠乏などが寄与することもあるだろう。福島原発事故について、人間を含め生体の複合的な反応を理解するためには、慣例的な放射線生物学・放射線物理学を超えた環境研究がこれからも必要である。
2017/02/11
Robustness and radiation resistance of the pale grass blue butterfly from radioactively contaminated areas: a possible case of adaptive evolution
放射能汚染地域のヤマトシジミにおけるロバストネス及び放射線抵抗性:適応進化の可能性を示す事例
[第9報] ヤマトシジミ(Zizeeria maha)はこれまで、2011年3月に起きた福島原子力発電所の事故による生物学的影響の評価に用いられてきた。本研究では、このチョウが汚染環境に適応することで健全性を維持している可能性を検討した。2012年5月に、事故後7世代目にあたるヤマトシジミの成虫を汚染程度の異なる7地域で採集し、これらの成虫20個体(n = 20)より幼虫2,432個体(n = 2432)を得た。これらの幼虫に沖縄の非汚染食草を与え、人工放射線照射のない自然暴露条件下で飼育したところ、汚染程度の最も低い地域のみでなく、最も高い地域の個体群においても、高い正常率(ロバストネス*を示す)が見られた。また、これらの幼虫に非汚染食草を与え、外部照射条件下で飼育した場合、及び、福島の汚染食草を与えることにより内部照射条件下で飼育した場合についても、同様に正常率を求めた。その結果、自然暴露条件下での正常率と外部照射条件下での正常率、及び、自然暴露条件下での正常率と内部照射条件下での正常率の間には、いずれも相関が見られた。このことから、放射線抵抗性(あるいは感受性)は、総体的な健康状態を示すものと捉えることができる。さらに、外部照射条件下での正常率、及び内部照射条件下での正常率を、自然暴露条件下での相対的な正常率で割ることにより、抵抗性を示す値(抵抗値)を求めたところ、高度汚染地域の個体群において最も高い抵抗値が見られ、福島第一原子力発電所からの距離と抵抗値との間には、負の相関が見られた。これらの結果から、汚染地域のチョウが事故後およそ1年間で、汚染環境に適応した可能性が示唆され、これは汚染地域においてその後観察された、死亡率及び異常率の低下の要因のひとつとなった可能性がある。
*訳注:健全性(本稿では、生理機能の相対的な正常率)。
2016/09/18
Fukushima’s lessons from the blue butterfly: A risk assessment of the human living environment in the post-Fukushima era
ヤマトシジミによるフクシマの教訓:ポスト・フクシマ時代の人間の生活環境におけるリスク評価
[第8報] 福島原発事故による生物学的影響を探るために行われた一連のヤマトシジミによる研究は、3つの重要な教訓を与えてくれる。第一に、日本でのヤマトシジミのような環境指標生物を持つことの必要性である。普通種であり(絶滅危惧種ではなく)、ヒトと生活環境(大気、水、土壌)を共有し、室内実験に利用可能な種である必要がある。原発事故の発生前および発生直後に、このような環境指標生物をモニタリングすることは、初期被曝による急性の影響を反映するものと考えられる。世代間をまたぐ長期的な影響の解明には、継続的なモニタリングが求められる。第二に、放射線のみの選択的な影響に限定せず、汚染地域における実際の健康状態を理解すること、さらには、汚染による影響の全体像を把握することが肝心である。我々のヤマトシジミを用いた実験では、福島由来の食草を幼虫に与え、全身的な影響を検証するため、(放射線特異的な症状や生化学マーカーではなく)生存率や形態異常率に注目した。その結果、電離放射線のみが環境かく乱の唯一の要因ではないことが示唆された。原子炉からの飛散微粒子は、その放射能に関わらず重要だと思われる。最後に、我々の研究は、単一の種内もしくはある地域個体群内においてさえ、放射能への感受性に相当の差が存在することを示している。以上の結果に基づくと、ヒトでの高い感受性は、機能的なDNA修復酵素の活性が低いだけではなく、呼吸器における微粒子への免疫学的な反応にも起因する可能性がある。ヤマトシジミから得られたこれらの教訓は、ポスト・福島時代において、地方及び国際レベルで、今後の放射能汚染への研究と、核政策や環境政策のために貢献できるだろう。
2015/12/9
Ingestional and transgenerational effects of the Fukushima nuclear accident on the pale grass blue butterfly
ヤマトシジミにおける福島原発事故の内部被爆的・継世代的影響
[(第7報)] 内部被爆影響と継世代的な影響に焦点を当ててこれまでの研究をまとめた論文
この論文では、これまでの研究でヤマトシジミ(Zizeeria maha)において明らかになったことやそこから考えられることについて、内部被曝と継代的影響に関することを中心についてまとめた。
ヤマトシジミは幼虫のときに汚染された植物の葉を食べると、たとえ低い線量であっても一部の個体で形態異常が生じたり死んでしまう。しかしその一方で、それらの個体以外では、形態異常としては影響が現れない。この感受性の違いは放射線耐性の適応進化の基盤となる。また、放射線量の変化に伴う形態異常率および死亡率の変化は、ワイブル関数やべき関数のモデルにあてはまった。さらに、親世代が汚染されたエサを食べて育った場合、その子世代が汚染されたエサを摂取すると高い死亡率を示した。しかし、これらの子世代でも汚染されていないエサを食べれば死亡率は低い水準に回復する。
我々の2011~2013年における野外調査では形態異常率と死亡率のピークは主に2011年秋となっており、その後は減少していき正常なレベルにまで戻った。これらの発見は初期の被曝のインパクトの大きさと特定の期間における継世代的な影響の蓄積を示している。しかし、個体群は3年以内、15世代以下という比較的短い期間で正常な状態に戻った。
2015/2/10
Spatiotemporal abnormality dynamics of the pale grass blue butterfly: three years of monitoring (2011-2013) after the Fukushima nuclear accident
ヤマトシジミにおける異常率の時空間的な動態:福島原発事故後3年間(2011-2013)のモニタリング調査
[第6報] 事故後3年間のモニタリング結果をまとめた論文
2011年3月の福島原発事故による放射能汚染の生物影響についての長期間のモニタリングは、汚染地域に生息している生き物に何が起きたのかを理解するために必要である。そこで我々は、1世代の期間が約1か月であるヤマトシジミ(Zizeeria maha)を用いて、野外個体群(成虫)および飼育個体(野外採集個体の子世代)における異常率の空間的・経時的な変化を調べた。その調査は、福島市、本宮市、広野町、いわき市、高萩市、水戸市、つくば市の7地点で、2011年~2013年の3年間に春と秋、計6回行われた。
その結果、汚染地域においては成虫(野外)の異常率は、急速に増加し2011年秋(5世代目)にピークに達することがわかった(この現象は低汚染地域では見られなかった)。また、飼育個体における総異常率(幼虫、前蛹、蛹期における死亡と成虫期における形態異常を含む)も、2011年秋(5世代目)または2012年春(7世代目)でピークに達した。飼育個体の異常率レベルが野外個体よりも高かったことから、野外個体群では実際にはさらに多くの死亡と異常が出現していたことを示している。そして重要なことに、これらの野外個体群および飼育個体群での異常率の上昇は、2012年秋(11世代目)、2013年春(13世代目)には正常なレベルに戻った。さらに、同様の結果が、1分当たりの捕獲頭数の変化や地面線量だけでなく、原発からの距離と成虫の異常率との間でみられる相関係数の変化においても得られた。
これらの結果は、初期の世代で生理的・遺伝的な不利益が発生し蓄積するが、それらは後に減少し正常値に戻ることを明らかにした。これは、原発事故後における生物の動態についての現在までに得られている最も包括的な記録である。さらに、これらは、野生生物における人工的な汚染の生物影響を評価する際には世代時間や適応進化を考慮に入れることが重要であることも示している。
2014/9/23
Ingestion of Radioactively Contaminated Diets for Two Generations in the Pale Grass Blue Butterfly
ヤマトシジミにおける二世代にわたる放射能汚染食物の摂取
[第5報] 内部被曝による影響をさらに掘り下げた論文
本研究では、小型の蝶ヤマトシジミへの汚染食草の影響を詳しく調べた。食草は、東北2地域(本宮市:161Bq/kg、郡山市:117Bq/kg)、関東2地域(柏市:47.6Bq/kg、武蔵野市:6.4Bq/kg)、東海1地域(熱海:2.5Bq/kg)、および沖縄(0.2 Bq/kg)にて採集した。第一世代への影響に加え、2世代連続で汚染食草を与えた時の影響(継代効果)についても調べた。
第一世代では、東北地域の食草を与えた群において、沖縄の食草を与えた群よりも高い死亡・異常率、前翅の矮小化がみられた。また、死亡率はセシウムの摂取量に大きく依存していた。関東および東海地域の食草を与えた群の生存率は80%を維持したが、東北地域の食草を与えた群でははるかに低い値となった。第二世代では、東北地域の食草を与えた群の生存率は20%を下回ったが、沖縄の食草を与えた群では70%を超えた。第二世代における生存率は、第一世代の摂取した放射線量に依存するものではなく、第二世代の摂取した食草に依存していることを示している。さらに、第二世代でも前翅の矮小化がみられ、これは2世代を通じたセシウムの累積摂取線量と相関があった。このことから、第一世代の摂取した食草もまた、第二世代へ影響を与えることを示唆している。
汚染食草由来の放射線による生物学的影響は、放射性物質の摂取量が少量の場合でも検出され得る。影響は継代的だが、非汚染食草の摂取により回復することも可能であった。このことから、観察された影響のうち少なくとも一部は、非遺伝的な生理的変化に起因することを示唆している。
2014/8/14
Fukushima's Biological Inpacts: The Case of the Pale Grass Blue Butterfly
福島原発事故の生物学的影響:ヤマトシジミの場合
[第4報]ここまでの研究のまとめ的な論文
この論文では、これまでの調査で明らかにしてきたことやそれらが意味していることは何かという点について、あらためて丁寧にまとめた。 これまでの研究を振り返ってみると、事故直後から調査を開始した事で汚染地域で起きた生態学的なダイナミクスを理解することができたと思われる。つまり、事故直後からの調査によって我々は放射線への抵抗性が獲得される進化の過程をリアルタイムで観察できた可能性がある。
また、我々の経験から、汚染が生じた時の生物への影響を調べる際の指針として以下のことを提案する。環境汚染がもたらす生物学的影響を明らかにする、あるいはその効果によって生じる分子的なメカニズムを明らかにするためには、まず、野外におけるデータを集めること、そしてその野外での現象を実験室内で再現することが重要であり、これら2点を基礎とした研究デザインを組んでいくべきである。
※この論文は著作権の関係で現在は日本語訳は掲載しておりません。
2014/5/15
The Biological Impacts of Ingested Radioactive Materials on the Pale Grass Blue Butterfly
ヤマトシジミにおける放射性物質摂取の生物学的影響
[第3報] 内部被曝の影響を定量化して評価した論文(2014年)
ヤマトシジミを用いて、放射性セシウム摂取線量と死亡率および異常率との関係を定量的に評価した。沖縄で採れた幼虫に、汚染区域で採集した食草を与えたところ、セシウム摂取線量に応じて死亡率・異常率が低線量レベルで急激に上昇した。この線量と異常(死亡)率との関係は、べき関数モデルに最も適合し、そのモデルから示される半数致死線量と半数異常線量は、幼虫1個体に対して1.9と0.76Bq、体重1kgあたり54000と22000Bqであった。また、蛹(さなぎ)内の放射性セシウムの残留率・蓄積率は、いずれもセシウム摂取量が最も低い場合に最も高い値を示した。これらの結果から、少なくともヤマトシジミにとっては汚染された食物を食べる危険性は実在しており、他のいくつかの生物にとっても危険性があるだろうと結論付けられる。
2013/8/12
The Fukushima Nuclear Accident and the Pale Grass Blue Butterfly: Evaluating Biological Effects of Long-term Low-dose Exposures
福島第一原子力発電所事故とヤマトシジミ:長期低線量被爆の生物学的影響
[第2報] 第1報へ寄せられた疑問や批判に対する反論やコメントを解説した論文(2013年8月)
2012年8月9日にScientific Reportsで発表した研究論文に多く寄せられた以下の11点の疑問点や質問等についての答えを明確化した。(1)ヤマトシジミには指標生物として多くの利点がある。(2)福島地方の個体の翅(ハネ)サイズの矮小化、(3)発達遅延。(4)福島地方で観察された斑紋異常は、外部・内部放射線照射実験や突然変異誘発剤により生じる斑紋異常に類似していることから、遺伝子変異によるものである可能性が示唆。(5)ヤマトシジミは福島地方で少なくとも50年間にわたり豊富な個体数を維持(事故以前の福島県産の標本を提示)。(6)2011年5月から同年9月にかけて異常率の上昇が見受けられることから遺伝子変異の蓄積が示唆。(7)観察された形態異常は遺伝性を持つ。(8)ヤマトシジミを採集した地点は津波の影響はない。(9)研究に用いた個体数は統計的に有意な結果を得るのに十分。(10)飼育は標準的な飼育方法で行われ、対照群では正常な成虫個体を得た。(11)照射実験により、野外採集の結果が再現。
昆虫細胞は一般的に短時間の高線量放射線照射には高い抵抗性を示すと考えられてきた。しかし、ヤマトシジミにおいては外部、内部からの長時間の低線量放射線照射に高い感受性を示した。この不一致は実験手法の違いから生じると説明できると考えられる。低線量の長時間放射線被曝における生物への影響の解明はまだ始まったばかりであり、福島第一原発事故の生物への影響の正確な評価にはさらなる研究が必要である。
2012/8/9
The Biological Impacts of the Fukushima Nuclear Accident on the Pale Grass Blue Butterfly
福島原子力発電所事故のヤマトシジミへの生物学的影響
[第1報] ヤマトシジミによる放射能汚染関連研究の最初の論文(2012年8月)
福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の拡散が、日本で普通に見られる小型の蝶であるヤマトシジミへの生理的・遺伝的損傷の原因となっているということを示した。2011年5月に被爆一世代目の成虫を福島地域で採集したところ、比較的軽度の異常を示す個体がいくつか見られた。被爆一世代目(親世代)のメスから産まれた子世代(F1)には、親世代より高い異常が観察された。この異常は孫世代(F2)に遺伝した。2011年9月に採集した蝶には、5月に採集たものよりも過酷な異常が観察された。同様の異常は、非汚染地域である沖縄の個体を外部および内部被曝させることにより、実験的に再現された。これらの結果から、福島原発由来の人工放射性物質がヤマトシジミに生理的・遺伝的損傷を引き起こしたと結論する。
その他の出版物
2015/11/5
The Biological Impacts of the Fukushima Nuclear Accident on the Pale Grass Blue Butterfly
福島原子力発電所事故のヤマトシジミへの生物学的影響
[国際フォーラムプロシーディング]
2014年11月29日にジュネーブで行われた「電離放射線の遺伝的影響についての科学と市民フォーラム(Scientific and Citizen Forum on the Genetic Effect of Ionaizing Radiation")」のプロシーディングです。 日本、アメリカ、フィンランド、イングランド、ドイツから6人の専門が招待され、講演を行いました。そのフォーラムの内容を主催であるIndipendentWHOがまとめたものが本プロシーディングになります。我々の研究室からは野原千代さんが発表を行いました(Pp93-105)。発表時の質疑応答なども掲載されております。また、表紙には野原さんへの献辞も掲載されています。
このプロシーディングはIndipendentWHOのホームページのプロシーディング特設ページからから無料でダウンロードできます。青字になっている"Read or download the Proceedings"をクリックしてください。
大瀧研から発表した関連論文
ABTプロジェクト
2016年度
避難指示解除地域における生物学的リスクの検討プロジェクト
指定解除された(される予定の)地域において、そこに生息する生物の状態や生息する生物がどの程度のリスク(放射線に対する)を負っているのかを実際に調べて、避難指示解除の妥当性について新たな視点から検討してみようという試みです。
メディア
※世界各地で取り上げていただいたメディアを紹介します。古いものはリンクが切れていることがあるかもしれません。ご了承ください。